
法人が役員や従業員のために加入する福利厚生。その一つである法人保険を検討する中で、「年間保険料が30万円を超えると経理処理が複雑になる」と聞いたことはありませんか。この30万円という金額は、法人保険の損金算入を考える上で非常に重要な基準となります。特に2019年の国税庁によるルール変更がいつから適用されたのか、その内容を正確に理解しておくことが不可欠です。この変更により、生命保険や医療保険など、保険の種類や最高解約返戻率によって税務上の取扱いが大きく変わるようになりました。年間保険料が30万円以下の場合に適用される30万円特例(少額短期保険等の特例)や、保険料を通算して計算する必要があるケース、短期払いや終身払いが経理に与える影響など、知るべき点は多岐にわたります。掛け捨てタイプで全損になる保険もあれば、貯蓄性があり資産計上が必要な保険も存在し、この特例が将来的に廃止される可能性についても気になるところでしょう。この記事では、法人の医療保険料が年間30万円を超えた場合の損金算入のルールについて、基礎から分かりやすく解説します。
- 年間保険料30万円が損金算入の何を分ける基準なのか
- 30万円を超えた場合の具体的な経理処理と注意点
- 最高解約返戻率に応じた税務上の取扱いの違い
- 節税と福利厚生を両立させるための保険活用のヒント
法人 医療保険 30万円超えたら税務はこう変わる
- 損金算入の鍵は国税庁の30万円特例
- 法人保険の保険料は全額損金になる?
- 30万円以下の場合は損金算入できる?
- 全損になる掛け捨て保険の条件とは
- 法人契約で30万円を支払うと損金は?
損金算入の鍵は国税庁の30万円特例

法人保険における経理処理を理解する上で、中心となるのが国税庁が定めた「30万円特例」です。これは、正式には「定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い」に関する法人税基本通達の改正(2019年7月8日以降の契約が対象)の一部で、実務上の通称として広く知られています。
この特例の核心は、被保険者1人あたりの年間支払保険料が30万円以下であるかどうかで、損金算入額を計算する際の経理処理方法が変わる点にあります。
具体的には、年間支払保険料が30万円以下の場合、保険の最高解約返戻率に応じた簡便な方法で損金算入割合を計算することが認められています。一方で、30万円を超えると、より厳密な「原則的」な方法で資産計上額と損金算入額を計算しなくてはなりません。このため、経理処理の手間が大きく変わってくるのです。
この30万円特例は、中小企業などの経理負担を軽減する目的で設けられた側面があります。しかし、ルールを正しく理解せずに処理を行うと、税務調査で指摘を受けるリスクもあるため、正確な知識が求められます。
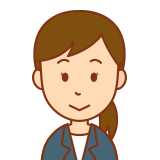
専門家ゆう
「30万円」という数字は、あくまで経理処理の簡便化を分けるラインです。「30万円を超えたら損金にできない」というわけではないので、混同しないようにしましょう!
法人保険の保険料は全額損金になる?

「法人保険の保険料は全額損金になる」という話を聞いたことがある経営者の方もいらっしゃるかもしれませんが、これは全てのケースに当てはまるわけではありません。保険料が全額損金として認められるかどうかは、主に保険の「貯蓄性」によって決まります。
この貯蓄性を判断する重要な指標が「最高解約返戻率(さいこうかいやくへんれいりつ)」です。
国税庁のルールでは、この最高解約返戻率が50%以下の保険については、その貯蓄性が低いと見なされ、支払った保険料の全額を損金に算入することが認められています。これは、年間の支払保険料が30万円を超えているかどうかに関わらず適用されるルールです。
一方で、最高解約返戻率が50%を超える保険については、貯蓄性があると見なされ、支払保険料の一部を資産として計上し、残りを損金として処理する必要があります。したがって、「法人保険=全額損金」という認識は誤りであり、保険商品の設計によって税務上の取扱いは大きく異なる点を理解しておくことが大切です。
30万円以下の場合は損金算入できる?

前述の通り、被保険者1人あたりの年間支払保険料が30万円以下の場合、「30万円特例」が適用され、損金算入額の計算を簡便的な方法で行うことができます。
この簡便的な扱いがどのようなものか、最高解約返戻率の区分ごとに見ていきましょう。
最高解約返戻率が50%超~70%以下の場合:
支払保険料のうち、損金に算入できる割合は60%です。残りの40%は資産として計上します。
最高解約返戻率が70%超~85%以下の場合:
支払保険料のうち、損金に算入できる割合は40%です。残りの60%は資産として計上します。
最高解約返戻率が85%超の場合:
このケースでは、支払保険料の大部分を資産として計上する必要があり、損金算入できる割合は非常に小さくなります。具体的な割合は、最高解約返戻率に応じて10%~30%の範囲で定められています。
このように、年間保険料が30万円以下であれば、保険の最高解約返戻率さえ分かれば、定められた割合を乗じるだけで損金算入額を計算できます。これにより、経理担当者の負担が大幅に軽減されるというメリットがあります。
全損になる掛け捨て保険の条件とは

法人保険において「全損」という言葉は、支払った保険料の全額を損金算入できることを意味します。節税効果を最大限に高めたい場合、この全損タイプの保険が選択肢に挙がることが多くあります。
全損として扱われる保険の最も代表的なものが、いわゆる「掛け捨て」タイプの保険です。
掛け捨て保険とは、解約しても解約返戻金がまったくないか、あってもごくわずかな保険商品を指します。税務上のルールで言えば、最高解約返戻率が50%以下の保険がこれに該当します。
全損として認められるための条件
保険料が全額損金となるための条件は、シンプルに最高解約返戻率が50%以下であることです。この条件を満たしていれば、その保険は貯蓄性がないと判断され、事業に必要な保障コストとして全額を経費計上できます。
具体的には、以下のような保険が該当することが多いです。
- 定期保険:保険期間が定められており、期間内に死亡・高度障害になった場合に保険金が支払われる。解約返戻率が低く設定されている商品が多い。
- 医療保険・がん保険(第三分野保険):入院や手術、がんと診断された際の保障がメインで、貯蓄性がない、もしくは低い商品が一般的。
- 収入保障保険:被保険者が死亡した場合、遺族が年金形式で保険金を受け取る保険。これも掛け捨て型が主流です。
したがって、保険料の全額損金算入(全損)を目的とする場合は、保険を検討する際に「最高解約返戻率」が50%以下であることを必ず確認することが最も重要なポイントとなります。
法人契約で30万円を支払うと損金は?

「法人契約で年間30万円の保険料を支払った場合、損金はいくらになるのか?」という疑問は、非常に実践的なものです。この問いへの答えは、「保険の最高解約返戻率によります」となります。
年間支払保険料30万円は、簡便的な計算方法が使える上限額です。そのため、経理処理は比較的シンプルです。具体例を見てみましょう。
【ケース1】最高解約返戻率が40%の医療保険に年間30万円を支払った場合
この保険は最高解約返戻率が50%以下のため、貯蓄性がないと見なされます。したがって、支払った保険料30万円の全額が損金となります。
【ケース2】最高解約返戻率が65%の定期保険に年間30万円を支払った場合
この保険は最高解約返戻率が50%超~70%以下の区分に該当します。30万円特例(簡便法)が適用されるため、損金算入割合は60%です。
計算式:30万円 × 60% = 18万円
この場合、損金になるのは18万円で、残りの12万円は資産として計上します。
【ケース3】最高解約返戻率が80%の長期平準定期保険に年間30万円を支払った場合
この保険は最高解約返戻率が70%超~85%以下の区分に該当します。30万円特例(簡便法)が適用されるため、損金算入割合は40%です。
計算式:30万円 × 40% = 12万円
この場合、損金になるのは12万円で、残りの18万円は資産として計上します。
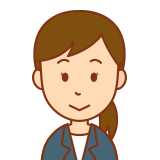
専門家ゆう
このように、同じ30万円の保険料でも、損金にできる金額は保険商品によって大きく異なります。契約前に保険会社から提示される資料で、必ず最高解約返戻率と税務上の取扱いを確認してくださいね。
このルールを理解することで、保障内容だけでなく、税務上のメリット・デメリットも考慮した上で、自社に最適な保険商品を選択できるようになります。
法人 医療保険 30万円超えたら知るべき経理の注意点
- 新ルールはいつから適用されたのか
- 生命保険も保険料を通算して計算
- 短期払いや終身払いの経理処理
- この特例が廃止される可能性
- 法人 医療保険 30万円超えたら専門家へ相談
新ルールはいつから適用されたのか
現在の法人保険に関する税務ルール、特に「30万円特例」を含む一連の取扱いは、2019年(令和元年)の税制改正によって定められたものです。
この新ルールが適用されるのは、2019年7月8日以降に契約した定期保険や第三分野保険(医療保険、がん保険など)です。逆に言えば、2019年7月7日以前に契約した保険については、原則として契約時の古い税務ルールが引き続き適用されます。
この「いつから」という基準日は非常に重要です。もし、現在加入している保険が複数ある場合は、それぞれの契約日を確認し、新ルールと旧ルールのどちらが適用されるのかを正確に把握する必要があります。経理処理を誤ると、後の税務調査で追徴課税などのペナルティを受ける可能性があるため、注意が求められます。
特に、2019年7月8日をまたいで保険の見直しや新規加入を検討した企業にとっては、この新ルールの理解が不可欠と言えるでしょう。
生命保険も保険料を通算して計算

「30万円特例」を適用するかどうかを判断する際、非常に重要な注意点があります。それは、1人の被保険者に対して複数の保険契約がある場合、その年間の支払保険料を「通算」して判断するというルールです。
例えば、ある従業員Aさんを被保険者として、法人が以下の2つの保険に加入しているとします。
- 医療保険:年間支払保険料 20万円
- 生命保険(定期保険):年間支払保険料 15万円
この場合、それぞれの保険契約の年間保険料は20万円と15万円で、どちらも単体では30万円以下です。しかし、30万円の基準を判定する際には、これらを合算します。
計算式:20万円 + 15万円 = 35万円
この従業員Aさんに関する年間の支払保険料は、通算で35万円となり、30万円の基準を超えることになります。その結果、この医療保険と生命保険の両方について、「30万円特例」の簡便的な経理処理は適用できず、原則的な方法で資産計上額と損金算入額を計算しなくてはなりません。
この通算ルールを知らないと、個々の契約が30万円以下であることから誤って簡便法で処理してしまい、税務上の誤りを犯すリスクがあります。役員や従業員ごとに、どの保険に加入していくら支払っているのかを正確に管理することが、適切な経理処理の第一歩です。
短期払いや終身払いの経理処理
法人保険の保険料の払い方には、保険期間全体にわたって払い続ける「終身払い」や「全期払い」の他に、保険料の払い込みを短期間で終える「短期払い」があります。この支払い方法の違いは、特に年間保険料が30万円を超える場合の経理処理に影響を与えるため、注意が必要です。
終身払いや全期払いの場合
終身払いや全期払いの場合、保険期間と保険料の払込期間が一致しているため、これまで説明してきたルールに従って、各事業年度で支払った保険料を資産と損金に按分していきます。経理処理としては比較的ストレートです。
短期払いの場合
短期払いは、例えば保障が一生涯続く終身保険の保険料を、60歳までや10年間といった短期間で払い終える方法です。この場合、1回あたりの支払保険料が高額になりやすく、年間30万円の基準を超えやすくなります。
短期払いの保険で年間保険料が30万円を超える場合、原則的なルールに基づいて経理処理を行う必要があります。この原則的なルールでは、支払った保険料のうち資産として計上すべき金額は、保険期間の初期段階(保険期間の40%に相当する期間)に集中します。
さらに、短期払いの場合、保険料の払込期間が終了した後も、それまで資産計上してきた「保険料積立金」を、一定の期間にわたって取り崩し、損金に算入していく作業が必要になります。
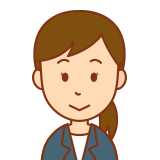
専門家ゆう
短期払いは、将来の保険料負担がなくなるメリットがありますが、経理処理は複雑化する傾向にあります。特に資産計上した積立金の取り崩し管理は、長期にわたるため注意が必要ですよ。
退職金の準備などで短期払いの終身保険などを活用する際には、保障内容だけでなく、このような長期的な経理処理の負担も考慮して検討することが賢明です。
この特例が廃止される可能性

法人保険の税務ルール、特に「30万円特例」について、将来的に廃止される可能性はゼロではありません。税制は、その時々の経済状況や社会的な要請、また制度の利用実態などに応じて、毎年見直しが行われるものだからです。
2019年のルール改正は、行き過ぎた節税目的での保険利用を是正するために行われました。もし今後、この30万円特例という簡便な措置が、新たな節税スキームの温床になるなど、当初の趣旨から外れた利用が目立つようになれば、国税庁が再び見直しに動く可能性は十分に考えられます。
ただし、現時点(2025年9月時点)で、この特例が具体的に廃止される、あるいは変更されるという公式な情報は出ていません。この特例は、中小企業の経理事務の負担を軽減するという正当な目的も持っているため、すぐに廃止されるとは考えにくい側面もあります。
法人保険を検討・活用する際には、目先の節税効果だけに囚われるのではなく、あくまで本来の目的である役員・従業員の福利厚生や事業保障を第一に考えることが大切です。そうすれば、仮に税制が変更されたとしても、保険契約そのものの価値が揺らぐことはないでしょう。
法人 医療保険 30万円超えたら専門家へ相談
ここまで見てきたように、法人の医療保険料が年間30万円を超えた場合の税務・経理処理は、非常に複雑で専門的な知識を要します。最高解約返戻率の計算、原則法による資産計上と損金算入の按分、複数契約の通算、払込方法による違いなど、考慮すべき点が数多くあります。
これらのルールを自己判断で解釈し、もし経理処理を誤ってしまった場合、税務調査で指摘を受け、過少申告加算税や延滞税といった追徴課税が課されるリスクがあります。これは企業にとって予期せぬ大きな損失になりかねません。
したがって、年間保険料が30万円を超える保険の導入を検討している、あるいはすでに加入している場合には、必ず専門家のアドバイスを求めることが賢明です。
相談すべき専門家
- 顧問税理士・会計士:企業の財務状況や税務全般を把握しているため、最も身近で頼りになる相談相手です。自社の状況に合わせた最適な経理処理方法について、具体的なアドバイスを受けられます。
- 法人保険に精通した保険代理店・ファイナンシャルプランナー:税務の知識はもちろん、多様な保険商品の中から、企業の目的(福利厚生、事業保障、退職金準備など)に合致した最適なプランを提案してくれます。
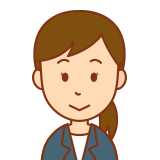
専門家ゆう
専門家に相談することで、税務リスクを回避できるだけでなく、より効果的な保険活用が可能になります。単なるコストとしてではなく、企業の成長を支える戦略的な投資として、法人保険を位置づけることができるようになりますよ。
適切な保障を確保しつつ、税務上のメリットを正しく享受するために、自己判断は避け、信頼できる専門家の力を借りることを強くお勧めします。
法人 医療保険 30万円超えたら専門家へ相談
- 法人保険の年間保険料30万円は経理処理の簡便化を分ける基準
- 30万円超は原則的な計算、30万円以下は簡便な計算が可能
- 損金算入の可否は最高解約返戻率によって決まる
- 最高解約返戻率が50%以下の保険は全額損金算入(全損)
- 最高解約返戻率が50%を超えると一部資産計上が必要
- このルールは2019年7月8日以降の契約に適用される
- 被保険者1人につき複数の保険料は通算して30万円基準を判断
- 生命保険と医療保険の保険料も合算して計算する
- 短期払いは経理処理が複雑になる傾向がある
- 終身払いや全期払いは比較的ストレートな処理となる
- 30万円特例が将来的に廃止される可能性もゼロではない
- 国税庁の方針や税制改正の動向を注視することが大切
- 経理処理を誤ると税務調査で指摘され追徴課税のリスクがある
- 自己判断は避け、顧問税理士などの専門家への相談が不可欠
- 法人保険に詳しい代理店も有効な相談先となる


コメント